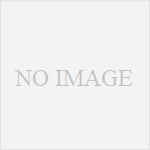レゲエは、単なる音楽ジャンルではなく、数多くのサブジャンルが発展し、個々の特徴を持っています。これらのサブジャンルは、ジャマイカやカリブ海地域の歴史、社会問題、そして文化的背景を反映しながら進化してきました。この記事では、レゲエの代表的なサブジャンルを紹介し、それぞれの特徴と魅力に迫ります。
ska(スカ)
スカは、ロックステディやレゲエの前身となる音楽ジャンルで、1950年代後半にジャマイカで誕生しました。
メント(ジャマイカのフォークソング)、カリプソ(カリブ海発祥の音楽)、ジャズやR&Bの影響を受け、生まれたと言われています。
非常にアップテンポ且つオフビート(裏打ち)のリズムが特徴で、ギターがリズムを刻むスタイルです。
実際に聞いてみましょう!
ザ・スカタライツはジャマイカの代表的なスカバンドで、この曲はジャマイカの独立を記念した曲だそうです。
その後、ジャマイカではロックステディに進化していきました。
また、1980年頃には、パンクと融合し、スカパンクなどのジャンルが誕生しました。
ROCKSTEADY(ロックステディ)
ロックステディは、1966年〜1968年にスカから進化したスタイルで、
スカの早い裏打ちのリズムをゆっくりにしたものがロックステディと言われています。
ロックステディを和訳すると、“落ち着いたビート”のような意味になり、名前の通りなのです。
ゆっくりになった理由として、
「早いテンポに疲れた」
「スカのレコードを遅く回した事により」
「R&Bの影響」
など諸説あるそうです。
また、ゆっくりになった事により、メロディにも特徴が現れ、甘く落ち着いた声で、ラブソングを歌われる事が多いのが特徴です。
ここではロックステディの名付け親とも言われているAlton Ellis(アルトンエリス)の楽曲を聞いてみましょう。
スカと比べてスローなテンポになっていることがわかると思います。
この曲には恋人と一緒にダンスを楽しもうというシンプルで甘いメッセージが込められています。
Early Reggae(アーリーレゲエ)
アーリーレゲエは、1969年〜1973年頃にロックステディから進化したレゲエの初期を指します。
アーリーの和訳が“初期”のなのでこちらも名前の通りになりますね。
SKINHEAD REGGAE(スキンヘッドレゲエ)とも言われています。
アーリーレゲエの特徴はロックステディゆっくりな楽曲に物足りなくなった事により、歌詞が攻撃的に変わっていきます。ここからレゲエは社会的問題などを歌うように変化してきました。
ここでは、Desmond Dekker(デスモンド・デッカー)の楽曲を聞いてみましょう。
一見、ロックステディと何が違うんだと思うかと思いますが、中身が違います。歌詞には、ジャマイカの労働者の厳しい生活や、植民地時代の影響による貧困と不平等が描かれています。
Israelites-和訳
たくさん働いても金が入らない
まるで犬のようにこき使われる
政府のやつらは気にもしない
何も悪いことはしていないのに
Roots Reggae(ルーツレゲエ)
ルーツレゲエは、1970年代にアーリーレゲエの影響を受け登場しました。
Roots Rock Reggae(ルーツロックレゲエ)とも言われています。
ルーツレゲエでは平和、愛、バビロンへの抵抗そしてラスタ思想(ジャマイカ人、黒人のルーツであるアフリカへの帰還を願う思想)が楽曲に組み込まれます。
レゲエの楽曲でよく耳にする”ジャーラスタファライ”などはルーツロックレゲエで生まれている事になります。これにより、ガ〇ジャチューンなども多く生まれました。
多くの人がレゲエと聞いて思い浮かべる楽曲はルーツレゲエに近いと思います。
ボブ・マーリーも代表的なアーティストの1人です。こちらも聞いてみましょう。
この曲には音楽の持つ力を信じ、自由と平等を求める気持ちが込められています。
Dancehall Reggae(ダンスホールレゲエ)
ダンスホールは、1970年代後半から1980年代初頭に登場した、クラブやパーティー向けのスタイルです。名前の通りダンスを踊るジャンルでもあります。
ルーツレゲエに比べてテンポは速くなり、これまで楽器の生音を使用されていましたが、電子音による打ち込みも使用されるようになります。
ダンスホールでは、「Toasting」と呼ばれるDeejayによるRiddimに言葉を乗せる技法が人気になり、たくさんのDeejayが生まれました。元々ルーツレゲエの合いの手として「Toasting」をし観客を盛り上げるDeejayがいて、その人たちが一曲フルで「Toasting」するようになり、新たなジャンルとして確立していったようです。
合いの手として、下ネタを言って盛り上げることもあったそうで、Deejayが下ネタを扱う由来はここからでしょうか。
「Toasting」は、HIPHOPのラップのルーツになっています。
またDeejayと共に、ラバダブ、ONEWAYなども人気になっていきました。
ここでは、ダンスホールアーティストYELLOW MAN(イエローマン)の楽曲を聞いてみましょう。
イエローマンはキング・オブ・ダンスホールと言われており、ダンスホールアーティストとして初めてメジャーデビューしたアーティストになります。
DUB(ダブ)
ダブは、1960年代後半から1970年代前半にかけて登場しました。
レゲエのインストゥルメンタル版(ボーカル抜き楽曲)に、エコーやリバーブ、ディレイなどのエフェクトを加える、主にRIDDIMが主役のジャンルです。REMIXの起源と言われています。
ジャマイカでロックステディが人気な頃、レコードのA面にメインの楽曲、B面にはA面のインストゥルメンタル版、という構成が主流でした。
このB面はレコーディングエンジニアによって、ミキシングされて作成されていたわけですが、その過程で、実験的に強くエフェクトを掛けることで、生まれたという説があります。
こちらも聞いてみましょう。
King Tubby(キング・タビー)はDUBの発明者と言われている、レコーディングエンジニアです。
DUBは登場してから現在のEDMまで、様々なジャンルに影響を与えているジャンルです。
ジャンルの枠を超え、音楽制作方法の一つでもあり、その先駆者であるキング・タビーは功績はとてつもないものでしょう。
Lovers Rock(ラヴァーズロック)
ラヴァーズロックは、1970年代中期にイギリスで登場した、メロウでロマンティックなレゲエスタイルです。
恋愛やロマンスに焦点を当てた甘いサウンドに多くファンが魅了されています。
この特徴はロックステディに似ていますよね。
そう、ラヴァーズロックはロックステディが起源になっています。ジャマイカではアーリーレゲエやルーツレゲエの登場で、ラブソングスタイルが衰退する中、そのスタイルはイギリスで進化してくのでした。
イギリスで進化したこのジャンルはジャマイカでも受け入れられ、多くのアーティストに影響を与えました。
ここでは、甘い雰囲気が伝わりやすいように日本人アーティストを例に挙げさせて頂きます。
ラヴァーズロックの甘い雰囲気が伝わったかと思います。asuka andoさんは日本を代表するラヴァーズロックシンガーです。
Ragamuffin(ラガマフィン)
ラガマフィンは、1980年代半ばから後半にダンスホールから派生したスタイルです。ラガとも言われています。
ダンスホールにさらに電子的な要素を加え、よりパワフルなフローが特徴的です。
ダンスホールからの派生なので、一括りでダンスホールとまとめられることが多いかも知れません。
ダンスホールの一形態と言ってもいいでしょう。
ダンスホールが基本的にパーティーやクラブで楽しもうというポジティブな内容(社会的なメッセージや政治的な批判を含む歌もある)なのに対し、
ラガマフィンは、貧困、暴力、ギャング、セクシュアルな内容、社会批判など、ストリートのリアルを反映したものが多いという違いがあります。
ただ、これらはどちらのジャンルにも言えることで、一概には言えないです。
ですので、電子的な要素が大きな違いになるのでしょうか。
※間違っていたら教えてください。
また、ラガマフィンという言葉の意味は”クールな不良“のような意味があるので、それがそのままジャンルのイメージになると思います。
今ではラガマフィンという言葉はジャンルよりも”不良“の意味で使われる事が多いです。
こちらも聞いてみましょう。
この曲は、ラガマフィンスタイルの始まりと言われており、完全デジタルRIDDIMの楽曲となっています。
「Sleng Teng Riddim」は”モンスターリディム”とも言われるほど人気で、レゲエアーティストを名乗る以上、このRiddimに乗れないと話にならないと思われるほどです。
さらに驚きなのが、そんなRiddimが、日本のメーカー”カシオ”から1981年に発売された、電子キーボード「カシオトーンMT-40」のプリセット音源だということです。
Ragga Hip-Hop(ラガヒップホップ)
ラガヒップホップは、1980年代後半から1990年代にかけて登場した、ラガマフィンのリズムやフローと、ヒップホップのサンプリング技法やビートが融合したものです。
ヒップホップのビートで、Deejayが歌うようなイメージでしょうか。
HIPHOPが世界中で人気を集める中、ジャマイカのプロデューサーはHIPHOPのビートで歌うようにアーティストに依頼するようになったそうです。
結果的に、レゲエとHIPHOPの双方向に影響を与え、たくさんのアーティストに影響を与えたと言われています。
実際、この時代にリリースされた曲には、このようにHIPHOP-REMIXが存在していたりします。
終わりに
このように、レゲエというジャンルは非常に多様であり、さまざまなサブジャンルが共存しています。
難しいからまとめてレゲエでいいじゃんと思う方もいるかと思います。
実際、ダンスホール系なのか、ルーツ系なのかくらいの判別で見分けている方が多いのではないかと思います。
これらのサブジャンルは、それぞれ異なるリズムやテーマ、音楽的な特徴を持ちながらも、すべてがレゲエの一部として、ジャマイカの文化や社会情勢に強く影響されてきました。そのため、サブジャンルをまとめて「レゲエ」と呼んでも、音楽的にも文化的にも一貫した流れとして自然に受け入れられると思います。